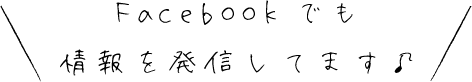2025.09.19
【金庫巡り】#8 三井本館に行ってきました
こんにちは!
兜LIVE!編集部です。
この連載【金庫巡り】では、この日本橋兜町・茅場町周辺にある古い金庫にフォーカスして、その歴史や魅力を発信していきます。第八回となる今回は、三越前駅に位置する「三井本館」を訪れました。現在も三井住友信託銀行と三井住友銀行として使われており、三井住友信託銀行の地下にある金庫も現役です。
◆三井住友信託銀行とは?

三井住友信託銀行は、1925年に誕生した、我が国で最初の信託会社の流れを受け継ぎ、2012年に住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行の3行が合併して誕生した、日本最大級の専業信託銀行です。
「The Trust Bank」を掲げ、銀行業務と信託・資産管理を一体的に提供する総合的なサービスを展開。個人の資産形成や相続はもちろん、法人・機関投資家向けのソリューション、不動産や金融マーケット関連など、幅広く手がけています。長い歴史と豊富な実績を背景に、「信じて託す」という理念のもと、を中核に据えて資産の保全と成長を支える中核的な金融機関として位置づけられています。
そんな三井住友信託銀行の日本橋営業部・東京中央支店が入っているのが、歴史的建造物として知られる「三井本館」です。1929年に竣工したこの建物は、1998年に国の重要文化財にも指定されました。現在も現役のオフィスビルとして使われており、日本橋を象徴する存在のひとつといえます。この建物には三井住友信託銀行と三井住友銀行日本橋支店の両方が入居しており、二つの銀行が同じ屋根の下にあるという珍しいケースとなっています。
◆三井住友信託銀行の「東洋一の大金庫」

三井住友信託銀行の地下にあるのが今回のお目当ての金庫です。現在も現役の貸金庫として機能しています。金庫内の広さは317㎡で貸金庫の数は6338個、扉の直径は2.5m、厚さ55cm、重さはなんと50トンもあるのだそう。大きさはもちろんのこと、堅牢さ、精巧さにおいて「東洋一の大金庫」とされています。
この金庫は、1929年にアメリカのモスラー社が特別に作ったもの。モスラー社は世界で初めて耐火金庫を作ったメーカーです。扉は異なる金属を組み合わせており、扉の外から熱が加わったときに膨張率の違いを使って外と中を遮断するという、耐火性に優れた作りになっています。これは、関東大震災で旧三井本館が内部の焼失を経験したこととも関連しています。

その甲斐あって、太平洋戦争や東日本大震災の際も無傷だったそうです。メンテナンスは基本的に年1回、錆止めの油を塗り、機能に問題がないかチェックしているそうです。

開閉はひとりで行うそうで、担当者さんいわく、「一度動き始めると意外に動くんですよ」とのこと。記者も特別に押させてもらいましたが、たしかに動くけれど、ずっしりとした重みを感じました……!
アメリカで作られて運ばれてきたこの大きな金庫の扉は当初、東京湾から陸路で三井本館まで運ぶ算段でした。しかし、重すぎるという理由で日本橋を通る許可が下りず、新常盤橋の際まで水路で運んだ上で、釣り上げたという逸話が残っています。

現在も貸金庫として機能しているこちらの大金庫ですが、実はここには、戦時中に集められたダイヤモンドが保管されていたという逸話も残されています。1944年、軍需省が兵器製造用の工具に用いるため、民間から大量のダイヤモンドを買い上げました。ところが戦局の悪化で実際に使われることはほとんどなく、終戦時には取引を担った財団によって保管されたままに。終戦後には、そのダイヤがこの地下金庫に保管されていたといいます。のちに連合国軍総司令部(GHQ)によって接収され、日銀の地下金庫へ移された記録が残っており、最終的に独立回復後に日本側へ返還されました。数十万カラットにも及ぶダイヤがこの金庫を経由したというエピソードは、金融史の一幕として今も語り継がれています。
金庫の扉は一般の人でも少し離れた場所からなら見学することが可能。夏休みに見に来る親子連れも多いのだそう。ちなみに撮影はNGです。見学を希望の場合は、必ず職員に見学の旨を伝えて、案内に従ってくださいね。
◆歴史の足跡が残る三井本館の見どころ

1902年に竣工した旧三井本館は、その20年後、1923年に関東大震災に見舞われました。躯体そのものは無事だったものの、震災復興に対して三井が範を示すため、また今後の事業拡大を見据えて現在の三井本館を建てることとなりました。関東大震災の2倍の揺れが来ても壊れない建物を作るべしと当時の三井合名社長の三井高棟が命じ、それに加えて理事長の團琢磨は「壮麗」「品位」「簡素」の3つのポリシーを掲げたといいます。設計はアメリカのトローブリッジ&リヴィングストン事務所、施工をジェームス・スチュワート社が手掛け、20世紀におけるアメリカの新古典主義様式が採用されました。
外装には花崗岩が使用され、内部は大理石がふんだんに用いられています。階を貫いてそびえるローマ風のコリント式大オーダー列柱が整然と並んでおり、まるで海外の駅舎や美術館のような美しさです。

初代社長室は当時のまま残っており、現在は部長室として使われています。実は三井本館は、1932年に起きた血盟団事件の舞台でもあります。政財界の要人でもあった三井合名理事長の団琢磨が暗殺されたのは、三井本館の三井住友銀行側の玄関。物騒だった当時、この社長室内に護身用の銃が隠されていたのだそう。
◆まとめ

日本橋・兜町の街並みは時代とともに少しずつ姿を変えていますが、その中心には常に金融の歴史が息づいてきました。
その中心に建つ三井本館は、90年以上の歴史を刻みながら、現在も三井住友信託銀行や三井住友銀行の拠点として活躍しています。地下に眠る「東洋一の大金庫」は、戦時中のダイヤモンドの逸話など数々の物語を秘めつつ、いまも貸金庫として人々の資産を守り続けています。外観を眺めるだけでも十分に歴史を感じられるので、日本橋に訪れた際はぜひ足を止めてみてはいかがでしょうか。
▪️過去の金庫めぐりシリーズはこちら
******************
▼兜LIVE!(かぶとらいぶ)
人と歴史と未来をつなぐ応援プロジェクト兜LIVE!では、たくさんの方が兜町・茅場町に親しみを持っていただけるような楽しく勉強になるイベントを企画・実施していきます。FacebookやInstagramをフォローして最新情報をチェックしてくださいね。
・Facebook
・Instagram
・X(旧Twitter)
×
兜LIVE!について
運営 |
一般社団法人日本橋兜らいぶ推進協議会 |
|---|---|
代表者 |
藤枝昭裕 |
住所 |
〒103-0026 |
連絡先 |
support@kabuto-live.com |