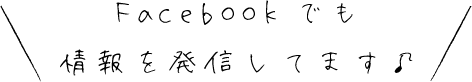2025.02.26
【蔵元トーク】#73 作(三重県鈴鹿市 清水清三郎商店)
こんにちは!
兜LIVE編集部です。
12月28日(土) 、『日本酒を蔵元トークとテイスティングで楽しむ』を開催しました。
今では国際金融都市といわれる日本橋兜町。
江戸時代には日枝神社の門前町として栄え、酒問屋で賑わっていた「日本酒の聖地」でした。
東京証券取引所において、上場時の5回の鐘撞は、酒の原料である五穀豊穣にちなんでいるとのこと。
平日は賑わうこの兜町に、休日にも人が集まってもらいたい。そんな願いから日本各地の蔵元を招き日本酒について学び、味わい、楽しく交流し、その魅力を、兜町の魅力といっしょに広目、お酒が地域と人をつなぐ場所...。そんな場所に発展するように願いを込めて、毎月1回日本酒セミナーを開催しています。
今回は、三重県鈴鹿市で「作」を醸す清水清三郎商店の代表取締役清水慎一郎さんをお迎えしての開催でした。清水さんは、蔵元トークがスタートした2017年以降7回目のご登壇となります。過去6回、その時々の話題をお聞かせ頂いています。今回はどんなお話を聴けるのか楽しみです。
◆ 最近の話題
・12月に日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されました。現在、日本酒は日本国内において消滅しそうなぐらいシェアが少なくなっているので、盛り上げていきたいと思います。
・TBSのネットからの写真ですが、この麹を造っているのは当社の内山杜氏です。写真提供は文化庁とありますが、無形文化遺産の申請をするのが夏場の7月ぐらいで、この季節に酒造りをしている蔵があまりないこともあり、文化庁から国税庁を通じて、撮影依頼がありました。

◆ 日本における酒の居場所
・18歳から成年とし、選挙権を付与することになりましたが、当然、選挙権だけではなく、飲酒、喫煙、賭博なども18歳から良いのではないかという意見が出されました。

・ところが、医師会の会長が撤回を要求したことから、急速にその話はなくなりました。

・業界では、それまでお酒は20歳になってからではなく、「未成年の飲酒は法律で禁じられています」と記載していたのですが、成年は18歳からとなったため、瓶の裏張りの文言を「お酒は20歳になってから」に変更するなど、対応が少し大変でした。
・選挙権は世界中でどうなっているのか調べたところ、日本はアメリカやイギリスと同じ18歳で、他の国はいろいろあります。

・お酒の飲酒可能年齢ですが、アメリカ(赤)は21歳と結構厳しめで、日本(ピンク)は20歳です。注目すべきはフランス(水色)です。フランスでは16歳になったら、親など監督する人間がいれば飲んで良いことになっています。

・この仕組みは、素晴らしいことだと思っています。日本人の平均的なアルコール分解酵素を持っている県のランキングです。

・三重県はなんと一番低いのです。一番高いのは秋田県です。欧米人はほぼ100%に近い確率でアルコール分解酵素を持って生まれてくるそうです。
・日本ではお酒を飲めない人が3分の1程度いるということなので、親など監督する人がいたら飲んでも良いというのは、素晴らしい仕組みだと思います。飲めるかどうかわからないのに、知らないところでお酒を飲んで泥酔したら大変です。監督がいる環境下でお酒を飲む勉強・訓練をして、飲めるのか飲めないのかを知ることは重要なことです。20歳になったからお酒を飲んでも大丈夫と勘違されては困ります。
・例えば、「教養としてのワイン」という本がありますが、以下のような記載があります。

・美術や文学などと並び、重要な教養のひとつとして深く生活に浸透しているのです。学校からビジネスシーンまで、さまざまなところでワインの教育が重要視されています。もちろんそれは、ワイン伝統国のフランスやイタリアだけの話ではありません。英国の名門大学、ケンブリッジとオックスフォードでは、60年以上にわたり、大学対抗のブラインドテイスティング大会が繰り広げられています。ブラインド対抗にのぞむ学生たちは、日々ワインを嗜み、味や香りを覚え、畑やヴィンテージ(ぶどうの収穫年)による微妙な違いを学んでいます。
・スイスでは16歳からワインの飲酒が法的に認められていますが、ボーディングスクール(全寮制の学校)では、16歳の女の子たちが10代にして、既にぶどうの特徴、作り手のスタイルを理解してます。ワインが必須科目として授業に組み込まれ、10代からワインを学ぶ場が提供されているのです。友人同士が集まるランチの場でも、食事に合わせてそれぞれが好みのワインを選びます。
・上述のとおりワインは教養として身につけなければいけないという社会的な共通の認識がありますが、日本で教養としての日本酒という認識はあるでしょうか。「日本酒が好きです」と言ったら、悲しいことにただの酒好きだろうと思われてしまうことが多いのではないでしょうか。海外から和食や日本酒が注目されているので、日本酒は日本文化として、ワインと同じようにしっかり教養を身につけないといけないと思います。
・習近平がイギリスへ行った時の話で、イギリス王室でワインが出されたのですが、⺠主化を求める学生を中国当局が武⼒で鎮圧、多数の死傷者を出した天安門事件と同じ1989年のワインだったそうです。それを習近平が「美味しい!美味しい!」と言って飲んでいるのを横でニヤニヤ笑っているイギリス人の意地悪さなのかもしれませんが、ちゃんと教養として知らないと恥をかくということです。
・フランスでは、大統領がアメリカを訪問した際の晩餐会でどんなワインが出されたによって、大統領が歓迎を受けているのかどうかを測るための一つの情報として注意しているそうです。

◆ 日本酒の海外動向
・お酒の種類別出荷量(数量ベース)の推移です。全体のアルコール出荷量がちょっとずつ減少しています。一番下の赤いところが日本酒で、どんどん減少していてほぼ6%です。特定名称酒は日本酒全体の3割しかないので、アルコール全体の1.8%ということは、100人いたら2人弱の人しか特定名称酒を飲んでいないということです。日本酒と名前がついているのに日本では飲まれない。本当に絶滅しそうな文化遺産だということが現状です。

・ビールもどんどん減っており、ビールの代わりに増えて来たのがチューハイや第三のビールなどテレビのコマーシャルでよく見かけるものです。
・一方で、日本酒は海外への輸出が増えていますので、日本国内の市場開拓もやっていかなければいけませんが、海外にもよく行きます。

・2014年9月にモスクワにおいて「日本・ロシアフォーラム2014」が開催され、日本酒のサーブなどをしました。若いですね(笑)

・その時、ロシア産スパークリングワインのラベルに「シャンパーニュ」と記載されていたのです。「シャンパーニュ」とは、シャンパーニ地方で造られたものだけで、それ以外は「スパークリングワイン」などと記載しなければいけないのですが、2021年にロシア政府はロシアで造られたものを「シャンパーニュ」と呼ぶとする法律を制定してしまいました。ロシアは原産地呼称制度に関する条約に加盟していないため、自国で勝手に決められるという理屈のようです。ロシアはフランスのシャンパーニメーカーにとって大きな市場だったのですが、その後どうなったのかは把握していません。

・今年2月にモナコで開催された国際ソムリエ協会の年次総会に行って来ました。そこでお酒を提供したほか、パーティーに参加しました。

◆ 和食の世界進出
・「ガストロノミー」という⾔葉がよく使われます。これを「美食学」と訳すだけでは、この⾔葉の持つ意味の背景を十分に表すことができないのではないでしょうか*。
*「ガストロノミー」という言葉の検索結果
―― ガストロノミー(仏:gastronomie、英:gastronomy)とは、食事と文化の関係を考察すること。料理を中心として様々な文化的要素で構成される。(ウィキペディアより)
―― ガストロノミーとは、料理という言葉が食材を調理する方法を指すのに対し、料理を中心として芸術、歴史、科学、社会学などさまざまな文化的要素を考える総合的な学問。文化と料理の関係を考察すること。(コトバンクより)
―― ガストロノミー(Gastronomy)とは、食文化や食に関する研究、料理の芸術、食材の起源や品質についての探求を含む、食に関する広範な領域を指す用語です。ガストロノミーは食文化の専門家や食通、シェフ、食品評論家、料理愛好家などの間で非常に重要なテーマとなっています。(ChatGPTより)
・フランス語の「ガストロノミー(gastronomie)は、ギリシャ語の「ガストロニミア(gastronomia)」が語源で、17世紀前半から使用され始めた⾔葉とされており、ガストロノミーは元々「胃袋(gastro)」と「規範(nomie)」から作られた⾔葉だそうです。「胃袋を支配する」ことを意味し、「フランスの食文化」として根付いている⾔葉です。19世紀から20世紀にかけて、フランスの旅と食の楽しみについて書かれた本が出版されるなど、フランス料理の多様性や芸術性について、多くの考察がなされました。こうした流れの中、20世紀後半から21世紀にかけて、ガストロノミーは、学問的な研究としても発展し、地理学や歴史学だけでなく、社会学や文化人類学などでもガストロノミーの研究は進み、その先進的な考え方は、フランスから世界へと広がりました。こうした背景の中に、ワインの理論的考察も行われています。

・日本酒はどんどん輸出が増えていますといわれていますが、実は日本酒の蔵元がいろいろなところに行ってプロモーションをやっているからではなく、和食の地位が非常に高くなり、和食店が世界中に広まった結果だと考えています。
・昔は、ニューヨーク、ロンドン、パリでも日本食の定食屋さんがあって、駐在員がそこに行ったらかつ丼や天ぷらなど懐かしい日本食を食べ、日本酒を熱燗や冷やで飲めました。ところが、ここ10年ぐらいは客単価が5万円、10万円の高級和食店がどんどん進出して、そういうところでパック酒を提供するわけにはいかないので、少し高いお酒や地酒などが扱われることが多くなりました。その勢いで輸出が伸びていったのではないでしょうか。
・和食とは全く関係のない三ツ星レストランの店でも、和食の手法を取り入れた料理が提供されることが増えてきました。例えば、和食とは関係のない料理屋さんでハマチとか茶碗蒸しが提供されるようになりました。最初、これで茶碗蒸しなんだと思ったら、卵でちょっととじたものだったのですが、出汁は熟成させた豚肉を日本の鰹節削り器で削って、それでダシを取った茶碗蒸しでした。そんな具合に日本食の手法が一流のシェフにとって今話題になっていて、「私は既に日本食をちゃんと勉強して知っているよ」ということがトレンドのようです。
・こんな時代はこれまでなかったでしょう。そこでガストロノミーの話が出てくるのですが、うまければ何でも良いということで、そういったお店では、日本酒や料理についてしっかり説明することはしない。一方、ソムリエは「これはどういうお酒で何と合う」といったような話をしなければいけないわけですね。フランスの「PIC」という三ツ星レストランに行きましたが、そこでいろいろ説明を受けながら食事を楽しみました。

・ソムリエが料理のお口直しに玉露を注いでくれました。こんな形で日本のことをちょっとずつ勉強しています。右側の写真は、フランスのクラマスターの審査委員長をやっているグザビエ・チョイザのお店で当社のお酒を手に持ってくれているところです。
・今、ソムリエたちが日本酒に対して非常に興味を持ってくれています。これは非常に素晴らしいことです。パリの和食店に卸しているインポーターは、もうパリでは日本酒は飽和状態にあると口を揃えて言います。現実に、彼らが行く和食店には既に日本酒が入っていて、もう新しいお酒を入れる余地はないといった話なのですが、ソムリエから話を聞くと、日本酒に興味はあるが、どこから仕入れれば良いか分からないそうです。そこに商品の流れのミスマッチがあり、興味ある日本酒を欲しがっている人達が手に入れることができるような仕組みを作っていかなければいけないと思っています。
・今年11月にセルビアのベオグラードで国際ソムリエ協会のヨーロッパ、アフリカ、中東のベストソムリエを選ぶ大会がありました。そこで各国の代表者が集まって、最後の5日目には3人に絞られ、その3人の中から優勝者を決めます。予選は見せてもらえなかったのですが、決勝戦は街の劇場の舞台で開催され、見せてもらえました。ソムリエの選手たちはマイクを着けて1人ずつ順番に課題にチャレンジします。
(課題)ここに3人います。この人たちに食前酒をサーブしてください。時間は5分です。
選手:何がいいですか。
A:私はカリフォルニアのシャンパーニュをください。
選手:シャンパーニュはこれですか。カリフォルニアはシャンパーニと言わないのですよ。
B:私は純米大吟醸をお願いします。
選手:これでいいですか。これはこういう料理に合いますよ。
・このやり取りを審査員が採点します。課題は7つあって、そのうちの1つに次の課題がありました。
(課題)8人のテーブルにモルドバの赤ワインをサーブしてください。時間は8分です。
選手:(モルドバの赤ワインを探してきて)これでいいですか。皆さん同じもので良いですか。
8人:はい、良いです。
選手:(デカンタージュし、3人目にサーブして注いでいる状況で)
5人目:私はにごり酒が欲しい。
選手:えっ!(全員のサーブを終え、獺祭にごりのスパークリングを持ってきて5人目に)これでいいですか。これはこういう料理に合います。
・3選手のうち1選手だけクリアして、後の2選手は時間切れでクリアできませんでした。その後、田崎真也さんにお会した際に、課題以外のことを突然言われて対応しなければならないのはどうなんでしょうかという話をしたら、田崎さん曰く「8人にサーブしなさいという課題は、通常6分で終えなければいけないので、8分と言われた時点で、「何か違う。隠し玉の課題が出てくる」と思わなければいけない」とのことでした。
・伝えたかったことは課題の内容ではなく、7つの課題のうち2問に日本酒が出題されたことです。さらに、にごり酒と言われてピンとこなければならない。世界中のソムリエは日本酒のことを勉強しないと優勝できないのです。
・再来年、ポルトガルのリスボンで世界最優秀ソムリエ大会が開催されます。日本からも誰か参加すると思いますが、ガストロノミーの話に戻すと、しっかり日本酒の味や料理との相性などを説明できないといけないということです。
◆ 伊勢の酒
・伊勢神宮の内宮神楽殿の東側に隣接する御酒殿があり、そこで毎年6月1日、10月1日、12月1日に御酒殿祭が行われます。ここで、由貴大御饌にお供えする御料酒(⽩酒・⿊酒・醴酒・清酒)がうるわしく醸成できるよう、また全国酒造業の繁栄を御酒殿の神にお祈りします。御酒(みき)と御饌(みけ)とは、「お酒」と「食物」という意味になります。

・日別朝夕大御饌祭は、内宮と外宮、別宮それぞれのご祭神にお食事を奉る神事で、外宮鎮座より約1500年間、朝夕の二度、禰宜1名、権禰宜1名、宮掌1名、出仕2名によって奉仕されます。
・神饌は、御飯三盛、鰹節、魚、海草、野菜、果物、御塩、御水、御酒三献と品目が定められ、それに御箸が添えられます。神饌は御饌殿の中で天照大御神を始め両宮と別宮のご祭神にお供えされ、禰宜が御饌殿の前で祝詞を奏上し、皇室のご安泰、国⺠が幸福であるようにと日々祈りが捧げられます。

・注目すべき点はここに4杯ありますが、3杯がお酒で1杯が水です。お酒を飲むときは和らぎ水と一緒に飲むということをアマテラスオオミカミはちゃんと知っているということです。
◆ 鈴鹿について
・「味酒鈴鹿国」(うまさけすずかのくに)という言葉は、当時、鈴鹿の国が美味しいお酒を造る土地として知られていたということであり、「味酒」(うまさけ)は「鈴鹿」の枕詞とされています。

・まだ広域に勢力を伸長していなかった大和朝廷は、攻め入られるリスクのある要衝の1つを関ヶ原、もう1つを鈴鹿峠としていました。そのため、鈴鹿には国府や国分寺が置かれていました。
・そんな鈴鹿に倭姫命(やまとひめ)が来た時の記述が「倭姫命世記」(やまとひめのみことせいき)に残されてます。倭姫命が鈴鹿を治める者に名を尋ねたところ、「味酒鈴鹿国『奈具波志』忍山」(うまさけすずかのくになぐわしおしやま)と答えたとあります。
・「なぐわし」は「名+ぐわし」で構成される古語で、「ぐわし」は「かぐわし」(香+ぐわし)に残っているように「素晴らしい」という意味です。良い言葉で、素晴らしい土地である「東条」の山田錦を使用したお酒の名前に使っています。

・なお、なぐわしシリーズはグッドデザイン賞をいただきました。

・ラベルデザインは神事などで使われる紙垂(しで)をモチーフにしています。紙垂は古来より邪悪なものを追い払うとして、神聖な境界を示すために使われました。3種類(「東条・山田錦」、「鈴鹿・神の穂」、「佐用・白鶴錦」)のデザインがあります。
◆ 日本酒の起源
・日本書記に出てくる酒に関する文章ですが、ヤマタノオロチは8つの頭のある大きな蛇で、稻田宮主簀狹之八箇耳(イナダノミヤヌシスサノヤツミミ)がスサノオに退治してくれと頼んだら、「たくさんの木の実を集めて、八個の甕(カメ)だけ酒を醸造しろ。」との記述があります。
・木の実は何かといえば、どんぐりでは酒を造れないので、ぶどうのことと思われるので、日本書記に書かれている最初の酒とはワインのことと推測できます。ヤマタノオロチの話が播磨風土記とか古事記にも書かれていて、播磨風土記では米と麹カビと記述があります。そのことをもって、GI播磨の中では日本酒発祥の地と記載しています。
・少なくとも日本書記では「木の実を集めて酒を造った」とあるので、ワインのことだと思います。ワインが最初にあったという前提で話をすると、150年前にワインが海外から入ってきたといわれていますが、日本人は昔からワインを知っていたことになります。

・ここからは想像で話です。
「王様達がお酒を飲んで食事をしていた。飲んでいるお酒はワインである。そこに家来が米と米麹で造った新しい酒を持って来た。王様達に勧めて飲んでもらうと、いつも食べている刺身、焼魚、イカの塩辛はワインには合わなかったが、今日飲んだ酒はこれらの料理と合った。それ以降、みんなで酒を飲むときはこの酒(日本酒)を飲もうということとなった。」
・先祖は日本酒しかないから日本酒を飲んでいたのではなく、主体的に日本酒を選んだという証拠です。それ以降、日本酒が飲まれ続け、発展して今の味になったのではないか推測できます。
◆ 【酒造⾒学ロケ】出張!りりらでん日本酒の会!〜作〜
・Vチューバー(バーチャルYouTuber)が蔵に来た様子で、結構面白かったので、見てください。
【酒造⾒学ロケ】出張!りりらでん日本酒の会!〜作(ZAKU)編〜【儒烏風亭らでん/一条莉々華/北白川かかぽ】
◆ 「美食の聖地・三重」
・三重県のお酒を売り込むのに、「美味しいお酒です」と言っても、どこの県も同じことを言います。そこで、三重県はちょっと違う形でPRすることにしました。三重県には伊勢海老、アワビ、牡蠣、フグ、松坂牛など美味しいものがたくさんあります。また、伊勢神宮があり巡礼の地で、日本中からたくさんの人が集まります。非常に長い歴史もあります。


・三重県は「美食の聖地」であり、そこのお酒ですというキャッチコピーでいきます。

・今後、誰かに三重県のことを聴かれたら、是非、「美食の聖地ですよ」と答えてください。こういう情報は、いろいろな方向から入ってくると、「え!知らないのは私だけ!?」ということになって、広まっていくものなので、ご協力のほどよろしくお願いします。
◆今回のお酒について
・3種類のお酒の説明です。

・今年のお正月は、能登の地震など本当に大変でした。来年こそは本当に良い年になることを願い、また、今日お集まりの皆様が健康で長生きして、身体を壊さずお酒をどんどん飲んでいただけるように乾杯したいと思います。乾杯!


◆最後はみんなで集合写真
・毎回、恒例の集合写真です。着物の方と海外の方が隣り合わせ。良いですね~!

◆まとめ
・清水さんは7回目のご登壇でしたが、今回も新鮮なお話をたくさん聴かせていただきました。再び三重県に行き、美食の聖地で「作」を味わいたくなりました。
みなさん、「美食の聖地・三重」を体感しましょう!

******************
▼兜LIVE!(かぶとらいぶ)
人と歴史と未来をつなぐ応援プロジェクト兜LIVE!では、たくさんの方が兜町・茅場町に親しみを持っていただけるような楽しく勉強になるイベントを企画・実施していきます。FacebookやInstagramをフォローして最新情報をチェックしてくださいね。
・Facebook
・Instagram
・X(旧Twitter)
×
兜LIVE!について
運営 |
一般社団法人日本橋兜らいぶ推進協議会 |
|---|---|
代表者 |
藤枝昭裕 |
住所 |
〒103-0026 |
連絡先 |
support@kabuto-live.com |