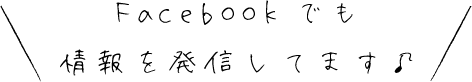2025.03.21
【蔵元トーク】#74 明鏡止水(長野県佐久市 大澤酒造)
こんにちは!兜LIVE編集部です。
2月8日(土) 、『日本酒を蔵元トークとテイスティングで楽しむ』を開催しました。
今では国際金融都市といわれる日本橋兜町。
江戸時代には日枝神社の門前町として栄え、酒問屋で賑わっていた「日本酒の聖地」でした。
東京証券取引所において初上場時の5回の鐘撞は、五穀豊穣に因んでいるとのこと。平日は賑わうこの兜町に、休日にも人が集まってもらいたい。そんな願いから日本各地の蔵元を招き日本酒について学び、味わい、楽しく交流し、その魅力を、兜町の魅力といっしょに広め、お酒が地域と人をつなぐ場所...。そんな場所に発展するように願いを込めて、毎月1回日本酒セミナーを開催しています。
今回は、長野県佐久市で「明鏡止水」、「勢起」を醸す大澤酒造代表取締役社長の大澤真さんに登壇していただきました。長野県からは2蔵めになります。どうぞお楽しみください!

◆ 自己紹介
・大澤家の14代目になります。第二次世界大戦の際に一度途絶えていますので、戦後私で2代目ということになります。小さい頃から家を継ぐことについて親に洗脳されていたので、幼稚園の頃から大きくなったら何になるのかと聞かれた際には酒蔵になると答えていました。とりあえずここまでやって来ていますが、次の代に引き継げるように一生懸命やっているところですので、皆さんの応援もよろしくお願いいたします。

◆ 大澤酒造株式会社について
・大澤酒造株式会社の所在地は赤印のところで、中山道沿いの望月宿と芦田宿の間にある茂田井になります。県庁(長野市)は黒印のところです。創業は1689(元禄2)年、現在は800石(一升瓶換算で約8万本)の造りです。
・代表銘柄は明鏡止水と勢起(せき)です。この2銘柄以外でも、地元では「大吉野」、「信濃のかたりべ」、「善光寺秘蔵酒」といった銘柄も造っていますが、現在は「明鏡止水」と「勢起」の2銘柄で90%になります。

・「信州佐久13蔵で醸す酒」とありますが、佐久に11蔵、隣の小諸市に1蔵、佐久穂町に1蔵となります。長野県全体では80蔵あり、そのうち13蔵が佐久にありますので、とても酒造りが盛んなところです。造っているお酒はそれぞれ個性がありますので、佐久に来た際はこの13蔵のお酒をぜひ飲み較べていただけますと幸いです。

・因みに、佐久は渋沢栄一と非常に縁が深いところになります。NHK大河ドラマ「青天を衝け」のタイトルは、内山峡にある渋沢栄一と尾高惇忠が佐久で詠んだ順信紀詩「内山峡の詩」の一節からとったものです。1858(安政5)年、渋沢栄一が19歳の時に師匠で義兄の尾高惇忠(28歳)と共に上州から東信濃へ藍玉の商いをしながら漢詩を詠んだそうです。そういったことから、NHK大河ドラマ「青天を衝け」が放送された時は非常に盛り上がったほか、新1万年札発行時も、地元ではいろいろな催し物がありました。

・創業の年は、松尾芭蕉が奥の細道に旅立った年と同じで、そういった時代に大澤家2代目の大澤一郎右衛門が酒造りを始めました。
・大澤酒造には、酒造り以外に3つの施設があります。
▼大澤酒造民族資料館
・1981(昭和56)年に元々お酒づくりの酛場だったところを改造して設立されました。
・きっかけは壺です。創業当時、最初に造ったお酒を古伊万里の壺に詰め、代々家宝として伝えています。先代(父親)がこれを使って大澤酒造を知ってもらいたいということで、1968(昭和43)年にNHKの「スタジオ102」という番組で壺を開けてお酒を分析してもらった結果、現存する日本最古の酒であるというお墨付きをいただきました。その分析をしていただいたのが発酵学の権威である坂口謹一郎先生でした。

・この壺をメインに蔵の中から小諸藩の藩主からいただいた甲冑や昔の巻物などをキャプション付きで展示しています。

▼しなの山林美術館
・先代が平成元年に元々お酒を瓶詰めするボトリング工場を改造し、叔父の大澤邦雄の喜寿を記念して設立されました。優しい木のぬくもりが感じられる館内では、文部大臣奨励賞受賞作の「聖域」をはじめ、日本山林美術協会員74人の作品などを展示しています。

・3年毎に提示する絵を入れ替えますので、3年に1回来ていただくと、違った絵を観賞できます。
▼名主の館 書道館
・先代が1997年(平成9)年に元々精米工場だったところを改装して設立されました。「現代書道の父」と呼ばれる比田井天来や天来門流作家の作品などを展示しています。

・比田井天来の孫弟子である吉野大巨が明鏡止水の字を書いてくださっているのですが、先生から蔵で空いているスペースをみて書道館にしたらどうかとの提案をいただき、書道館になりました。
・2部屋あるのですが、1部屋は桑原翠邦という天皇陛下の中学校時代の書道の先生の個展をやっており、ほぼ常設です。通常、蔵見学はやっていませんが、資料館、美術館、書道館は自由に見ていただけるようになっています。
・蔵の前の道が旧中山道で、遠くに見えるのは浅間山です。当社のお酒の仕込水は南側にある蓼科山の伏流水を使っていますので、中山道から見える浅間山ではないです。

・杉玉のぶら下がっている入口から中に入っていただくと、松、梅、竹があって、「松竹梅」が皆さんをお迎えします。

◆ 大澤酒造の歴史
・1689(元禄2)年創業以降、一郎右衛門という名前を襲名していましたが、2代目の一郎右衛門が酒造業を始めました。ただし、戦争が始まる前までは襲名していましたが、祖父が戦争で亡くなり、一時期酒造業をやめたので、現在は襲名していません。
・明鏡止水に関しては、1989(平成元)年に発売しましたので、まだそんなに歴史はありません。私も東京農業大学の醸造科ですが、卒業して東京の問屋さんで約6年働いた後、蔵に戻り酒造りスタートしました。もっとも、なかなか地元の酒屋さんに認めてもらえず、東京など県外で営業しました。純米吟醸のお酒をタンク1本造り、瓶燗火入れ(生でお酒を瓶に詰め、それを湯せんし、丁寧に火入れ)したお酒を持って酒屋さんを訪ねました。純米吟醸が1本から4本になった時に吟醸や特別本醸造なども造り始め、徐々にお酒の種類も増えていきました。
・2003(平成15)年に社長になったのですが、翌年に社員による酒造体制を確立しました。それまでは岩手県の南部杜氏組合にお願いして、毎年、杜氏、頭、麹屋、酛屋、窯屋の5名体制で来ていただき、お酒造りが終われば国へ帰るというパターンだったのですが、杜氏達も高齢化して、先行きが危なくなってきたので、地元で窯屋を採用して、次は酛屋、麹屋を採用しました。元々麹屋として採用したわけではなかったのですが、成長して社員でお酒を造れるようになりました。
・お酒は造りが50%、出荷管理が50%といいます。良いお酒ができても、最高の状態で瓶詰めや出荷ができないと元も子もないです。南部杜氏はお酒を造り終わると帰ってしまいますが、社員で造るとその後の瓶詰めや出荷など全部に関わり、例えば、自分たちが造ったお酒をお客様に最高の状態で届けるにはどうしたら良いかといったことも考えるので、酒造りへの愛情が最後まで途切れないということが現在の体制の良いところです。また、その情報が造りから出荷まで社員全員で共有できるので、これは何のためにやっているのかということも伝達できるほか、理解も深まります。課題は若い社員が定着しないことです。
・勢起というお酒は、明鏡止水の後に造ったのですが、コンセプトがしっかりしていなかったため、2014(平成26)年、 木島平村産金紋錦を100%使って低温熟成させたお酒を勢起としてリニューアル発売しました。
・2022(令和4)年、創業333周年を迎えたのですが、コロナだったため、記念碑を出した程度で記念すべき333周年は終わってしまいました。創業350周年は、そこまで生きているかどうかが分からないので、息子に任せたいと思います。

◆ 明鏡止水の方針
・長野県産米を中心に酒造好適米の特定名称酒のみを造っています。長野県産米では美山錦を一番使っているほか、次にひとごこち、山恵錦、金紋錦を使っています。このほか、兵庫県産山田錦や岡山県産雄町も使っています。蔵のお客様が「雄町で造ったらどんなお酒ができるか楽しみですね」とリクエストをいただいたのですが、どんなお酒になるか未知数だったので3年くらい断っていました。それでも「どうしても飲みたい。ぜひ造ってほしい」という熱意に負けて雄町で造りました。残念ながら今期はまだ雄町を造っていないのでお持ちできなかったのですが、発売された際はぜひ飲んでみてください。
・大澤酒造のお酒は、香りが高いとか、含んだ時に華やかに口の中で広がるとかを求めているわけではなく、あくまでもお酒は単体で飲むというよりは何かを食べながら飲むものだと考えています。それによって料理が引き立ち、料理を食べることによってさらにお酒が美味しくなることを求めています。マーケット的には香りが華やかで、口に入った時にふわっと広がるお酒の方が良い印象なのでしょうが、できれば何かを食べながらスイスイと杯を重ねられるようなお酒が良いと思っています。あくまでも当社のスタイルを貫き、今のお酒造りを続けていきますので、よろしくお願いします。

・明鏡止水は、年間を通して、純米吟醸、純米、辛口本醸造の3本柱ですが、季節に合ったスポット商品(限定品)も造っているので、楽しんでいただけると思っています。あまり香りがないお酒がベースとなりますが、先行き、こういうお酒が主流になると信じて酒造りをしています。
◆ 勢起(せき)の方針
・勢起は「勢いよく起きる」と書くのですが、これは私の曾祖母の名前です。明治、大正、昭和と大澤家を精神的に支えてくれた偉大なる曾祖母の名前を銘柄にしています。女性で「勢いよく起きる」と書く名前は珍しく、すごいことだと思っています。「当て字ですか」と言われることがありますが、墓石にもちゃんと「勢起」と書いてあるので間違いありません。それだけ精神的に強い曾祖母だったということですね。この名前をいただいて、孫である株式会社花山の大澤千金社長が命名しました。
・勢起は1967(昭和42)年9月6日に享年91歳で逝去しました。現在、お酒を造っている私の弟が1967(昭和42)年7月2日生まれで、勢起が亡くなる前に生まれていますが、勢起の生まれ変わりということで、本人は気合を入れて造っていると申しておりますので、お酒を飲んでいただけましたら幸いです。

・勢起のブランドコンセプトは、「しみ滋味旨い」です。原料米は長野県木島平村の金紋錦を100%使用して生酛仕込みです。純米酒と純米大吟醸を造り、1年以上低温熟成させます。金紋錦は長野県で3千俵ぐらいしか作られていないお米なので、幻の米といわれることもあります。山田錦が父親、たかね錦が母親で、どちらかというと粒の大きいお米です。このお米を使うとどのようなお酒にすると良いのかと考えた結果、1年以上熟成に耐えられるお米ということで、低温熟成で発売しています。さらに、生酛仕込みという乳酸を添加するのではなくて、空気中にある乳酸菌を取り込んで造ったお酒になります。当初は純米吟醸も造っていたのですが、少し味がぼけるということで、現在は純米と純米大吟醸だけにしています。
・生酛造りに関しては、皆さんの頭の中にきっと生酛だとこういった味わいがするだろうというイメージがあると思います。当蔵の生酛は「飲んでお酒の良さが伝わる」、「飲んで美味しい」、「綺麗な生酛」で、その生酛のお酒をさらに保管するともっと美味しくなります。日本酒は冷やでも温めても美味しいのですが、この勢起に関していえば、特にお燗が合う造りになっています。
・勢起2種類(生酛 純米、生酛 純米大吟醸)の共通点は、「香りはほのか」、「枯れた奥深い味わい」、「寒上がりの素晴らしさ」、「熟成を手軽に」となります。勢起は熟成させていますが、老香(ひねか)を感じなくて、美味しく飲めるのはお米(金紋錦)や生酛という造り方の力ということを分かっていただけるのではないかと思っています。

◆ 最後に
・「伝統的な酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されました。日本酒は国酒であり日本の文化なので、これが世界的に認められたということはとても喜ばしいことです。今後も益々酒造りを一生懸命やっていきます。

◆今回のお酒について
・テイスティングしていただく3種類のお酒の説明です。



では、乾杯!


◆最後はみんなで集合写真
・毎回、恒例の集合写真です。楽しい時間はあっという間ですね。

◆まとめ
・長野県佐久市の蔵を訪問した際も、大澤酒造は料理に寄り添う酒質の追及ということで、地元の美味しい料理に合わせてお酒を飲ませていただき、料理とお酒の相乗効果で幸せな時間、空間を楽しむことができました。ぜひ、佐久市に行って明鏡止水、勢起を飲みましょう!

******************
▼兜LIVE!(かぶとらいぶ)
人と歴史と未来をつなぐ応援プロジェクト兜LIVE!では、たくさんの方が兜町・茅場町に親しみを持っていただけるような楽しく勉強になるイベントを企画・実施していきます。FacebookやInstagramをフォローして最新情報をチェックしてくださいね。
・Facebook
・Instagram
・X(旧Twitter)
×
兜LIVE!について
運営 |
一般社団法人日本橋兜らいぶ推進協議会 |
|---|---|
代表者 |
藤枝昭裕 |
住所 |
〒103-0026 |
連絡先 |
support@kabuto-live.com |