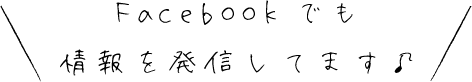2025.05.09
【かぶかや・ヒューマン】 #25 中野晴啓さん なかのアセットマネジメント
日本を代表する金融の街、日本橋兜町。明治時代に渋沢栄一によって興されたこの街に、2023年9月、生活者のための長期投資を手がける「なかのアセットマネジメント株式会社」が誕生しました。
この会社を立ち上げたのは、資産運用の世界で長年にわたり実績を積み上げてきた前セゾン投信社長 中野晴啓さんです。中野さんは、日本に「長期」・「積立」・「分散」投資の考え方を広め、浸透させた立役者でもあります。
そんな中野さんはなぜ、兜町でオフィスを構えることにしたのでしょうか。その背景には、これまでのキャリアや兜町への深い想いがありました。なかのアセットマネジメントの創業理由、中野さんが感じる兜町の魅力なども含めて、詳しく話を聞きました。

◆「長期投資の本質」を追求する。個人向けの投資信託運用会社を設立した背景
――改めて、貴社の事業内容をお聞かせください。
単純に申し上げますと、当社は投資信託の運用を行っている会社です。生活者の皆さんが資産形成をしっかりと実践できるよう、長期で保有できる投資信託を提供しています。実は、私たちは兜町の中でもやや特殊な存在です。近年、兜町に本社を構える資産運用会社の数は増えていますが、個人向けの投資信託を専門とした企業はほとんどないのが現状です。
――お客様は個人の方が中心なのでしょうか。
はい、法人向けの案件は扱っておらず、全国の個人のお客様を対象に事業を展開しています。私たちが目指しているのは、日本全国およそ1億2,000万人の生活者すべてがお客様となるような資産運用サービスです。
――なぜあえて個人のお客様をターゲットに会社を立ち上げようと思われたのか、そのきっかけを教えていただけますか。
私は長年、主に機関投資家向けの資産運用の仕事に携わってきました。機関投資家は一度に大きな資金を預けてくれますし、効率的にビジネスを進めるうえでは非常に魅力的な取引相手です。しかしその反面、基本的には半年から1年ごとの短期的な成果を厳しく求められます。
そんな世界で私は、「この仕事は、本当に社会の役に立っているのだろうか?」という疑問に行き着きました。そしてその問いを突き詰めていく中で、「長期投資」が本来持つ意味や意義を、改めて見つめ直すようになったのです。
その結果たどり着いたのが、全国の一人ひとりの生活者から少しずつお金をお預かりし、それを長期的な視点で丁寧に運用していくという、今のスタイルです。投資の本来あるべき姿を取り戻したい——この思いこそが、私がこの会社を立ち上げた原点なのです。

――本来の投資とはどういうものなのでしょうか。中野さんの考えをお聞きしたいです。
投資とは本来、素晴らしい企業を見つけ出し、その企業がさらに成長し、社会により良い価値を提供できるよう、資金面から支援することだと考えています。では、「素晴らしい企業」とはどのような企業でしょうか。それは、魅力的な商品やサービスを生み出し、人々の暮らしを豊かにし、笑顔を生み出している企業です。
ただ、人々に笑顔を届けるには、長い時間と大きな資金が必要です。投資の役割は、その「笑顔を生み出す力」を支えるために必要なお金を企業に提供すること。そして、その結果として人々の笑顔が生まれたときに、その「ありがとう」の気持ちをリターンとして受け取る。それこそが、本来の投資の意義だと私は考えています。
とかく、投資を「短期的な売買で利益を狙うもの」と誤解している人も少なくありません。1年で損切りをするとか、すぐに上がる株を探すといった行動が目立ちます。しかし本来、株価は相場の流れで上がるものではなく、企業が立派に成長した結果として評価されて上がるものです。これが長期投資の本質です。
私は、一人ひとりの生活者の方々からお金をお預かりし、思いを込めて素晴らしい企業に資金を届けることで、本当に意味のある長期投資を実現していきたいと考えています。だからこそ、私は投資信託という仕組みに、強い思いを持ち続けているのです。

◆兜町という街の記憶
――中野さんは社会人になりたての頃、兜町に何度も足を運んでいたそうですね。当時の兜町で特に印象に残っているエピソードや場所などはありますか?
私は新卒で旧セゾングループに入社し、金融子会社で法人資金の運用を担当していました。といっても、最初はアシスタントのような立場で、紙の株券を運ぶのが主な仕事でした。本社は山手線の西側にあり、兜町に勤務していたわけではありませんが、若い頃は頻繁にこの街を訪れていました。当時はちょうど1980年代後半、証券市場がバブルに沸いていた時代です。
場外取引では、株券の現物をすぐに届ける必要がありました。金額も大きかったため、株券を持ってタクシーで証券会社に向かうのが日常でした。到着すると、売買相手を目の前にして一枚ずつ株券を数えるのですが、50万株ともなると相当な量で、しかも紙幣のように柔らかくないため、指が痛くなることもありました。
そうした取引のあとには、証券会社の方が「ご苦労さん」と声をかけてくれて、「じゃあ、昼食でも食べに行こうか」と誘ってくださることもよくありました。大きな商談があった日には、「今日は特別だから、いい店に行こう」と言われることもあり、そんなときは、うな重などの豪華なランチをごちそうになるのが恒例でした。中でも「松よし(※)」には何度も連れて行っていただいたのを覚えています。兜町の思い出といえば、やはり鰻とセットですね。

松よし(※)
関連レポートはこちら
――当時の兜町の雰囲気はどのようなものでしたか?
当時は、今では統廃合によって社名が消滅してしまった証券会社がたくさんありました。大手・準大手に加えて中小の地場証券が30社ほど存在し、取引の中心は株券の現物でした。街はいたるところで本当に活気にあふれていましたね。
昼休みになると、白いシャツにネクタイ、上着はなしで運動靴を履いた人たちが一斉に通りに出てくるんです。彼らは「場立ち」と呼ばれる人たちで、その姿はとても独特でした。体格の良い人が多く、証券取引所の中では手話のような独自の合図を使って取引を行っていました。
面白いのは、その手話を外でも使っていたことです。大通りを挟んで会話をする時など、声が届かないので手話でやり取りする姿が見られたんですよ。そういった光景があちこちで見られて、兜町はまさに「取引所の街」と感じられ、独自の証券文化が息づいていました。
中でも、日経平均が当時の最高値38,915円を記録した1989年頃は、おそらく歴史上最も賑やかだったのではないでしょうか。

――その後の兜町はどのように変わっていきましたか。
バブル崩壊後、証券業界は深刻な不況に見舞われ、多くの証券会社が倒産しました。それに伴い、兜町で働く人の数も大幅に減少していきました。かつて証券会社が入っていたビルは、次第にワンルームマンションなどに姿を変えていき、街の様相も大きく変化しました。
活気にあふれていた兜町が、徐々に静まり返っていく――。その変わりゆく風景もまた、私にとっては強く印象に残る体験の一つです。
◆兜町は新しい金融の街へ変化を遂げている
――『Tokyo Financial Street 315』という番組を拝見し、兜町は「躍動している街」だとおっしゃっていたのが印象的でした。改めて、街のどのような姿を見てそう感じられたのでしょうか?
今の兜町を見てまず感じるのは、「おしゃれになった」ということです。ただし、単におしゃれな店舗を集めただけではありません。この街にしかない、個性豊かなお店が街のあちこちに点在している点が非常に魅力的です。大規模な商業施設ではなく、小さくても特色のある店が複数存在することで、自然な人の流れが生まれ、かつてバブル崩壊で失われた街の活気が、少しずつ戻ってきているように感じます。
さらに最近の兜町で特に素晴らしいと感じるのは、「フュージョン=融合」が自然に起きていることです。たとえば兜町のカフェでは、ベテランの金融マンも若い女性も、それぞれにランチを楽しむ姿が自然に混ざり合っています。これは、単に新しい施設を整備しただけでは生まれない、人と文化が自発的に交わっていく街ならではの魅力です。
私は、街づくりにおいて最も大切なのは「整えすぎないこと」だと考えています。すべてを綺麗に整えすぎると、かえって生活の実感や温かみが失われてしまう。だからこそ、昔ながらの細い路地や古い建物を残し、新しい要素と組み合わせていく「コンフュージョン=良い混沌」の存在が重要なのです。兜町には、まだその“雑然とした魅力”が息づいています。これからも、たとえば屋外の空間を仕事場として活用できるようにしたり、ベンチや屋台が並ぶような、自由度の高い環境づくりが必要だと感じています。そうした工夫が、この街のさらなる進化につながると信じています。

――「新しい金融の街になってきている」というお話も印象的でした。具体的にはどのような変化を感じていらっしゃいますか?
一番大きな変化は、兜町のコンセプトそのものが変わってきていることです。以前は「取引所=証券会社の街」というイメージでしたが、今や証券会社が主役ではなくなりつつあります。株式取引の多くはコンピューター上で瞬時に行われるようになり、かつて必要だった「場立ち」も不要になりました。証券会社の数自体も、もはやそれほど必要ではありません。
では今、何が必要とされているかというと、それは「資本市場でプレーする人」、すなわち資産運用業の存在です。取引所だけでは完結しない金融機能、たとえばヘッジファンドやプライベートエクイティといった、高度で成熟した社会に不可欠な金融業態です。欧米ではすでに広く普及していますが、日本ではまだ数が限られています。そうした新しい金融機能が、今まさに兜町に集まりつつある。それがこの街を再び「金融の中心地」へと変えている原動力だと感じています。

——今後、兜町という街にどのような進化を期待されますか?
私は、兜町が「運用の街」、すなわち「アセットマネジメント・シティ」として発展していくことを願っています。アメリカのボストンのような存在ですね。ウォール街もかつては金融ブローカーの街でしたが、今では運用会社が金融業の主役です。ロンドンのシティという街も同様に、資産運用会社が金融業界の中心となっています。
日本ではこれまで、金融の中心は銀行でしたが、社会の成熟とともに、資産運用の重要性が増してきました。「資産運用立国」という言葉が政策にも掲げられていますが、これからの日本では、資産運用こそが金融の中核を担うべきだと思います。
――なかのアセットマネジメントとしての展望や、今後の街との関わり方についてもお聞かせください。
当社としては、今後も事業に真摯に取り組みながら、私が18年前から発信してきた「長期投資」の考え方を、より多くの人々に届けていきたいと考えています。そして、日本における新しい金融の在り方を築いていく一助となれればと思っています。この兜町という街とともに歩み、共に成長し、次の時代の金融文化を育んでいけたらと願っています。
******************
▼兜LIVE!(かぶとらいぶ)
人と歴史と未来をつなぐ応援プロジェクト兜LIVE!では、たくさんの方が兜町・茅場町に親しみを持っていただけるような楽しく勉強になるイベントを企画・実施していきます。FacebookやInstagramをフォローして最新情報をチェックしてくださいね。
・Facebook
・Instagram
・X(旧Twitter)
×
兜LIVE!について
運営 |
一般社団法人日本橋兜らいぶ推進協議会 |
|---|---|
代表者 |
藤枝昭裕 |
住所 |
〒103-0026 |
連絡先 |
support@kabuto-live.com |